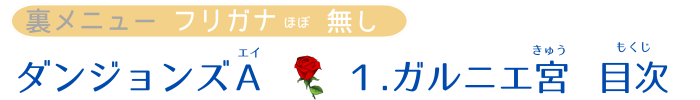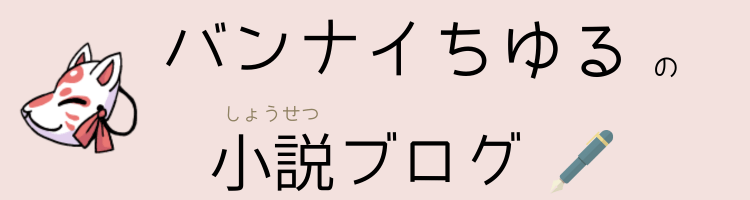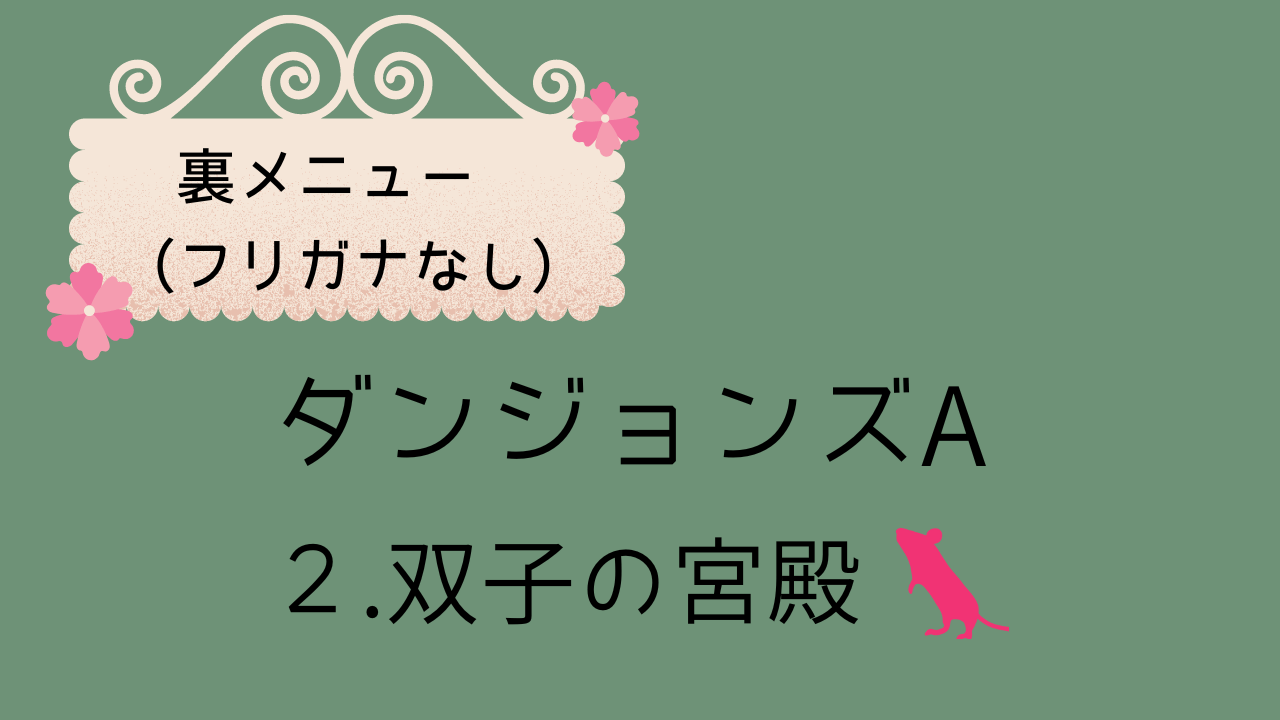当サイトは広告を利用しています プライバシーポリシー
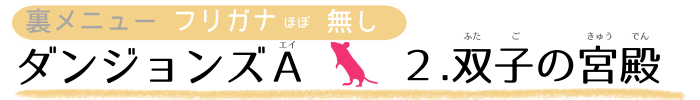
1.挿話 レンジで白玉(1)
碧が、ボウルの中の白い塊を捏ねている。
なかなか、まとまらない。
出来損ないの粘土みたいだ。
「少しづつ水を加えながら、力を込めて練っていく……だったよな」
レシピを信じて、忠実に調理を進める。
うん。だんだん、お餅らしくなってきた。
「ねー、碧。この缶詰、どうやって開けるの?リングが付いてないよ」
暁は、キッチンに並べた材料を、興味津々で弄りまわしていた。
碧と同様、調理実習用のエプロンを着けている。
でも、全く戦力になっていない。
「そこに缶切りがある。それで開けるんだよ」
頂き物の、粒餡の缶詰だった。
美味しさは、三ツ矢家お墨付きだが、今どきプルトップ缶ではない。由緒正しき形状だ。
ちなみに、偉そうに言っている碧も、暁のことを笑えなかった。
これを頂いた時、全く同じことを、母親に尋ねたのだ。
「できそう?」
自分の手は、べたべただ。
やってくれれば、ありがたい。
暁は、首を捻りながら、缶切りを手にした。
「う~ん?」
缶詰をくるくる回して、考え込む。
「どこから攻めればいいの?」
「わかった。俺がやる」
碧は、早々に諦めて、いったん手を洗った。
一回、やっただけだが、暁よりはマシだ。
缶切りの刃が、銀色の縁に斬り込んでいく。
きこ きこ
ゆっくりと上下に動かして進むと、切れ込みが入っていった。
「こうやって、ぐるっと切っていくんだって」
少し実演してみせただけで、暁は顔を輝かせて、ぴょんと跳ねた。
「わかった! やってみる」
やる気はあるのだ。
だが、いきなり碧は後悔した。
勢いが良すぎる。恐ろしいほど危なっかしい手つきだ。
代わらないで、自分がやった方がマシだった。
はらはらと、隣から口を出す。
「蓋のギザギザに気を付けろよ。手、切らないようにな。あ、最後は俺がやるから、もうちょっと切ったら代わって」
暁は、素直に交代した。碧に缶切りを手渡す。
ここまできたら、楽勝だ。
短い首を残して、蓋を持ち上げる。
慎重に折り曲げると、缶詰は、ようやく開いた。
「なんか……既に疲れた」
思わず溜息をつく碧とは対照的に、暁は満足気だ。
にこにこと、みっちり詰まった中身を見ている。
「おもしろかった。うん、美味しそう」
碧の気力が、一気に盛り返した。
「そう! 陽の家から貰ったやつなんだけど、本当に美味しいんだよ、これ」
中の粒餡をスプーンで掬ってタッパーに移しながら、力説する。
「あんこ万歳って言いたくなるから!」
この台詞は、伯母の受け売りである。
だが、母も自分も、最初に食べたときには、思わず復唱したものだ。
「ほら、暁」
最後に掬ったスプーンを、碧は手渡した。
大仰に言い渡す。
「つまみ食いを許してつかわす」
「わあ」
暁は、嬉しそうに声をあげると、餡子を口に運んだ。
「ん!」
目が真ん丸になる。本当だ。おいしい。
何が他と違うんだろう。
豆の風味が、そして砂糖の輪郭が、しっかりと感じられる。
暁は、両手を上げて、高らかに謳った。
「あんこ、ばんざーい!」
「よし。そうだろ」
頂いた日に開けた缶は、半分をバニラアイスに乗っけて味わい、残りを焼きたてホットケーキに添えて賞味した。
そこで、碧に欲が出た。
せっかくだから、この粒餡で、ちゃんとしたスイーツを作ってみたい。
だが、母親が渋った。
忙しくて、まず、そんな時間は取れそうにない。
自分だけで挑戦すると主張してみたが、小学生の身には問題があった。
火を使うのは、NGだ。
そこで、実奈子伯母さんに相談したところ、このレシピを教えてもらったのだ。
「これなら、レンジで作れるわよ。この料理家さんのは、もう絶対にお勧め!」
載っているレシピ本も、貸してもらった。
母親に説明し、許可も取った。
準備は万端だ。
かくして、子どもだけの料理教室と相成ったのだ。
まあ、はなから、暁に戦力としての期待はしていない。
碧は、練り上げた白玉粉をボウルから取り出すと、まな板の上に乗せた。
ころころ転がして、ひも状に伸ばす。
「これで、5等分する、と」
目分量で、5つに切り分けた。
「で、丸める」
「あ、私もやるよ」
暁も手伝う。
だが、二人の目の前に並んだ5個の団子は、明らかに大きさが違った。
「なんか……バラバラだな」
「大丈夫じゃない? このくらい」
鷹揚に言う暁に、碧が首を振る。
「火の通りが均一にならないと、仕上がりに差が出ちゃうだろ」
これも、実奈子伯母さんの受け売りだ。
野菜を切りながら、そう言ってるのを聞いたことがある。
「でも、どうやったら同じにできるかな?」
むー
二人で考え込む。
すると、傍らに置いてあるキッチンスケールが、碧の視界に入った。
「分かった! 量ればいいんだよ」
碧は、白玉の生地をひとまとめに戻した。
スケールの皿に乗っける。
デジタルの数字が表示された。
111
ゾロ目だ。単位はグラム。
「111÷5?」
暁が、ぱっと碧を見る。
「22.2」
碧の眼鏡が、光った。即答だ。
「まあ、小数点以下は無視だな。1個22グラムにしていこう」
碧が、ひとつひとつ量って、暁が丸めていく。
今度は上手くいった。ほぼ同じ大きさだ。
そこに、丸めた粒餡を包んで、まんじゅうを作り上げる。
いいぞ。この時点で、既に美味しそうだ。
皿に並べ、ラップをして電子レンジに入れる。
ほどなく、ピロピロと電子音が鳴り響いた。
窓に張り付いて見守っていた二人は、速攻で取り出した皿を確かめた。
ラップの内側に、水滴が付いていた。
剥がすと、売っている大福餅みたいな物が、きちんと出来上がっている。
「できてる!」
暁が、ぴょんぴょん跳ねた。
キッチンでのお行儀ではない。
だが、叱る大人もいないことだ。
碧も嬉しくて、立ったまま、皿に手を伸ばした。
「いいよ、ここで。暁も食べよう」
促された暁も、つい釣られた。
摘まみ上げると、柔らかな白玉まんじゅうをぱくりと頬張る。
お餅部分は、ふわふわだった。
中の粒餡も、ほくほくしている。
見た目も味も、大成功だ。
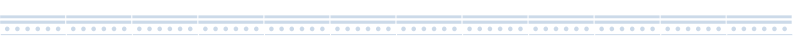


読んで下さって、有難うございます! 以下のサイトあてに感想・評価・スキなどをお寄せ頂けましたら、とても嬉しいです。
ランキングサイトにも参加しています。
クリックすると応援になります。どうぞよろしくお願いします↓