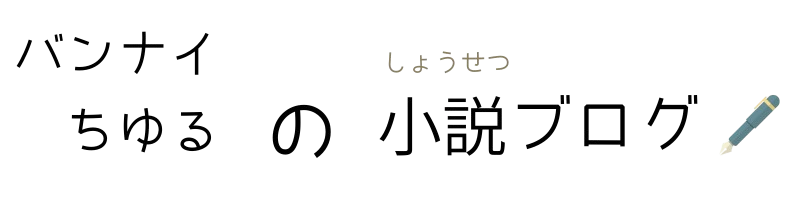当サイトは広告を利用しています プライバシーポリシー

1.挿話 たい焼きはあんこ・たこ焼きは大阪(1)
たい焼きの食べ方は、二通りある。
しっぽから食べる。
頭から行く。
どちらを取るかは、個人の好みだ。
このフードコートで統計を取ったら、どっちの食べ方が優勢なんだろう?
碧は、見渡しながら考察した。
ま、よく分かんないか。
とりあえず、このテーブルでは、頭から行く派が優勢だ。
ぱくり
暁は、大きな口を開けて、頭を齧った。
「あ、まだ、すっごい熱い!」
はふはふ天を仰ぎながら、もぐもぐと口を動かす。黒い餡子が、もう見えていた。
熱い餡子は、溶岩のように危険だ。
舌を火傷してしまう。
ふうふう
ぱくぱく
その合間に、「あちっ」と悲鳴を上げる。
たいへん忙しない。
碧は、カリカリのしっぽを小さく齧った。
ふわり、と生地の香ばしい匂いが漂う。
なかなかの優良店だ。しっぽの先まで餡子が入っている。
だけど、量は少ない。しっぽから食べ進めれば、お腹と頭に到達する頃には、いい感じに冷めているという塩梅だ。
「だから、しっぽから食べればいいのに」
苦言を呈した碧に、反論があった。
「う~ん。最初にガツンと餡子が来ないと、食べた気がしないじゃない?」
暁の母親だ。
頭から行く派、二人目の主張である。
そんな理由か?
でも、さすがに大人相手に突っ込めない。
碧は、無言で苦笑を浮かべるに留めた。
そんな碧を見て、暁の父親が肩をすくめた。
「理屈じゃないんだな、きっと」
今日は、暁の家族行事に参加している碧だ。
一ノ瀬家クリスマス恒例、バレエ「くるみ割り人形」の鑑賞会だ。
開演時刻まで、まだかなり余裕があったので、ここで時間を潰すことにした次第だ。
碧の母親も誘われていたのだが、この時期に仕事を休むのは、とうてい無理だ。
そんな場合、暁の母は、いつも碧だけを連れて出かけてくれる。保育園時代からだ。
いつだって恐縮する碧の母に、いつだって本音100%で答える暁の母であった。
「碧ちゃんは、しっかりしているから、ぜんぜん大丈夫。むしろ、暁のお目付け役が増えて、助かってるから」
事実であった。
暁は、幼少期から、実に何回も迷子になっている。興味をそそられたものに、後先考えず突進していく性質のせいだ。
でも、警察沙汰になった回数は、碧のおかげで半分くらいに抑えられている。
「暁、お水持ってきてくれないか?」
暁の父が、頼んだ。
彼のたこ焼きも、そうとう熱かったらしい。
まだ、全然減っていない。
ちなみに、たこ焼きも同様に危険だ。
うっかり熱いのを頬張ったら、最後。口の中で、マグマのような小麦粉の溶岩が流出する。
「あ、うん。みんな要るよね」
暁が、ぱっと席を立った。
フードコートの飲料水は、セルフサービスだった。
ちょっと離れた場所に、コーナーが見える。
結構、人が並んでいる様子だ。
碧も、食べかけのたい焼きをトレーに置いた。
全員分なら、手伝った方がいいだろう。
「ああ、いいよ。碧ちゃんは、まだ食べてるだろう」
暁の父が、優しく言った。
整った顔で、笑いかける。
暁が美少女なのは、確実に、この父の遺伝子によるものだ。
だが、その美少女も、口の端っこにたい焼きのしっぽを銜えた姿では、台無しだった。
立ったまま、もぐもぐしている。
「こら」
あんまりなお行儀に、暁の母が短く叱った。
まだ食べてるときに、立っちゃいけない。
「は~い。じゃ、これ捨てながら、お水汲んでくるね」
既に食べ終えている。
暁は、たい焼きの入っていた紙袋を折り畳むと、席を離れた。
「暁、手伝わなくて平気か?」
声を掛けると、暁は振り返って碧を見た。
「だいじょうぶ」
笑顔を浮かべる。
だが、どこか弱弱しかった。
いつもの、生き生きした笑みじゃない。
照度を計ったら、きっと何ルクスも劣っているだろう。
あの日からだ。
ずっと、暁は静かに元気がない。
こんな状態の娘に、母親が気付かないわけはない。
果たして、三人だけになったテーブルで、暁の母が、まっすぐに碧を見た。
齧りかけのたい焼きは、見苦しくないように、紙袋の中に沈ませている。
「ねえ、碧ちゃん。暁、ここんとこ元気がないんだけど、なんでかな?」
完全にストレートの球で来た。
暁の母らしい。
こちゃこちゃ策を弄したり、迂遠な言い回しで探ったりは、性に合わないのだろう。
竹を割ったような性格なのだ。
「やっぱり、空手、やめたくないのかな?」
隣に座る父は、首を傾げて碧に聞いてきた。
ちょっと寂しそうだ。
「空手やってレンジャーレッドになるんだって、いつも言ってたもんなあ」
幼い頃の、暁の口癖だ。
「いや、さすがに今は、レンジャーレッドは無理って分かってるでしょ」
碧は、すかさず返した。
父親の我が娘に対する認識は、そこで止まっているらしい。
「せやかて、しょうがないでしょ!」
暁の母は、そんな夫に畳みかけた。
「2月から、塾は6年生クラスになるんだし。授業日も増えるから、どうしたって空手の稽古日と被っちゃうのよ」
そうなのだ。
成績トップクラスの碧に至っては、さらに授業のコマが多い。ほぼ毎日塾に行く、中学受験生の日々が始まる。
「今は、とにかく受験。空手は、また中学から部活で続けようねって言って。暁も納得してるわ。だから、空手教室は、切りよく年内でお終いよ」
碧と暁が、抜ける。
その後の空手教室を考えると、碧だって悲しくなってしまう。だが、しかたがない。
「そうか……。あ、朱里さん、たこ焼き食べる?」
まだ全然減っていない舟皿を、夫は妻に差し出した。譲歩のつもりなのか。
ああ、だめだって。
碧は、内心、頭を抱えた。
どうして、何年も連れ添っているのに、学習しないのだろう。
それは、ヒートアップした妻に、さらに燃え盛れと言わんばかりに、燃料を投下する行為なのだ。
くわっ
一ノ瀬朱里は、目を見開いた。
「いらんわ、そんなん! タコが小っちゃくて、生地の中でアップアップ溺れとるようなたこ焼きやないの!」
大阪出身の妻は、一喝した。
大阪の血が、許さなかったらしい。
こと、たこ焼きに関しては、求める基準がどの県民よりも高く、厳しいのである。
「ははははは」
あーちゃんパパは、堪えた様子もなく、笑って返した。
この人も、優し気な容貌のわりに、神経が太い。
暁は、この父と母の、絶妙なブレンドで出来ている子どもだ。
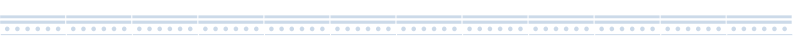


読んで下さって、有難うございます! 以下のサイトあてに感想・評価・スキなどをお寄せ頂けましたら、とても嬉しいです。
ランキングサイトにも参加しています。
クリックすると応援になります。どうぞよろしくお願いします↓