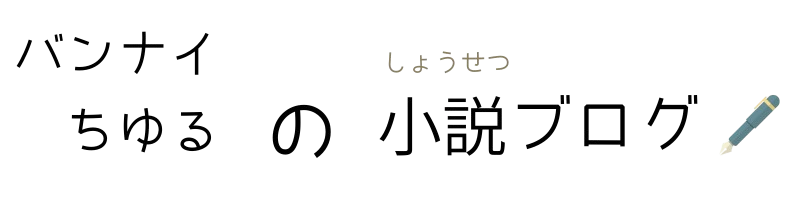当サイトは広告を利用しています プライバシーポリシー

1.〔挿話〕寒くなってきたら、湯豆腐(1)
昆布は、洗っちゃいけない。
手渡された布巾は、固く絞られていた。
カチカチに乾いた海藻の表面を、さっと拭き取って、汚れを落とす。これでいい。
「実奈子伯母さん。この土鍋に昆布を入れとけばいいんだよね」
もう、水が張ってある。
旨味を出すため、しばらく漬けておくのだ。
「うん。ありがと、碧ちゃん。じゃあ、陽は、これ、お願い」
小柄な伯母は、自分よりも大きな息子に、皮をむいた大根を手渡した。
見事な包丁さばきだった。
しゃべっている間に、切って剥いてパスだ。
キッチンは、実奈子伯母さん一人で、ほぼ満員状態だ。
申し付けられた陽は、数歩先のリビングルームに移動した。
置いてあるテーブルは、既に第二の調理台と化している。
だが、ここは食事をする場であると同時に、テレビを見て寛ぎ、さらに兄妹が勉学に励む机でもあった。
だから、大根をおろす際には、ペンスタンドをひっくり返さないよう、気を付けなければならない。
お世辞にも広いとは言えない家だが、利点はあった。
子どもたちの手を借り、夕飯の支度を進める総司令官にしてみれば、非常に都合がよい。
キッチンから動かずとも、一目で戦況が見て取れる。
「あれ? お母さん、唐辛子、一本しか入れないの?」
種を取って、水に漬けてある物を見て、陽が聞いてきた。
「いいでしょ、一本で。あんまり辛くすると、碧ちゃんが食べられないから」
「いや、俺なら、最近は割と辛いの大丈夫だよ。あ、でも桃ちゃんがダメか?」
隣で手伝っていた少女が、顔を上げた。
小皿にポテトサラダを盛り付けていた手を、いったん止める。
大人しそうな容貌の女の子だ。
切れ長の目に小さめな口が、優し気で可愛らしい。
左右に分けた髪を、両サイドで結い上げている。ヘアゴムには、ピンク色のボールが付いていた。
名前と同じ、小さな桃みたいな飾りだ。
碧より、一つだけ年下なのだが、もっと幼く見える。背も、ずっと低い。
こくり
桃は、頷いた。
「うん。あんまり辛すぎるのは、苦手」
とても小さな声だ。
だが、はっきりと答えた。
「んじゃ、やっぱり一本だな。って、陽、何やってるんだよ。穴は一つだけでいいんだろ」
ぶさぶさ
大根に菜箸を刺していた陽を、碧が遮った。
「あ、そうかあ」
もはや、レンコンみたいにボコボコだ。
白い大根の穴に、赤い唐辛子を埋め込む。
「残りはタダの空洞だな」
「まあ、おろせば関係ないだろ」
おろし金に、陽の腕力がフル稼働した。
みるみるうちに、赤く色づいた大根おろしが出来上がる。
ぴりっと辛い薬味。紅葉おろしだ。
「実奈子伯母さんって、ほんとに料理上手だよね」
碧が、お世辞抜きで褒めた。
自分の母は、湯豆腐の薬味に、ここまで凝ったりしない。
そもそも、土鍋でなんか出てこない。
二人だけの家に、鍋料理は不向きだ。
「やあねえ、碧ちゃんったら。そんな大層なものは作れないわよ。ただ、時間だけはあるからねえ、私は」
控え目に微笑みながら、一瞬たりとも調理の手は止めない。
確かに、豪華な献立ではなかった。
だが、碧が夕食に寄る土曜日は、いつだって多彩なメニューが並ぶ。
予算面での制約のもと、可能な限りのバリエーションを叶え、栄養面でも偏り無く。
まさに匠の技だ。
実奈子伯母さんは、手のひらで豆腐を切った。
水を張った土鍋の中に、そっと沈めていく。
深緑色の昆布を敷いて、白い直方体が、お行儀よく並んだ。
「陽、火を付けておいて」
土鍋を、テーブルに準備しておいたカセットコンロに移す。
この後は、子どもに任せて大丈夫だ。
次は、揚げている唐揚げの様子を見る。
ちょうどいい。油の中で、美味しそうな黄金色になっている。
したたたた……
菜箸が、鍋から唐揚げを引き揚げていく。
碧は、思わず見入ってしまった。
すごい。
連続突きをする陽よりも、素早い動きだ。
香ばしい匂いが、狭い部屋に漂った。
横では、陽がカセットコンロに燃料の缶を装着している。こちらも、迷いのない動きだ。
「陽って、それ、できるんだ」
「おー。碧、やったことないか? 火、付けてみる?」
「いいの? 大丈夫かな?」
尻込みする碧に、妹の方が答えた。
お箸を並べながら、呟くように言う。
「大丈夫。今日はお父さんいるから」
この小さな「はとこ」氏にも、碧は信を置いている。
時には、不愛想に取られてしまう女の子だ。
だが、無責任に、楽観的な言動をしないだけなのである。
お世辞やお追従も、言わない。
今回も、実に客観的な保証をしてくれたものだ。
「そうそう。万が一、火事になっちゃっても、お父さんに消火してもらえばいいしなあ」
気楽に笑う陽に、母親の鋭い喝が飛んだ。
「なに言ってるの! うちが火事なんか出してみなさい。大顰蹙よ」
もっともだ。
「碧ちゃんに、しっかり教えてあげなさい」
危ないから、やっちゃ駄目。
とは言わないのが、三ツ矢家だ。
おっかなびっくり。碧が、コンロのスイッチを捻った。
バチバチバチ
音に驚いて、つい慎重になりすぎた。
ゆっくりすぎて、点火しない。
「もっと思い切り回しちゃって大丈夫だよ、碧」
「このコンロ、かなり古いから。なかなか火が点かない時があるの」
横で見ていた桃も、冷静に教えてくれる。
「あら、点かない? チャッカマン持ってきなさい」
包丁をふるいつつ、実奈子伯母さんが、顔を上げずに言う。
「えええ! あの巨大ライターみたいなやつ? 使うの?」
碧の腰が引けた。できる気がしない。
「いや、点くだろ。碧、もう一回やってみな」
陽が、笑顔で促した。
重たげな土鍋の底を横から覗き込みながら、碧は思い切ってスイッチを回した。
ボッ
音を立てて、くるりと青白い炎が灯った。
「点いた!」
「な!」
陽が、碧よりも得意げな顔をする。
「あら、点いたの。チャッカマン、要らなかった?」
「うん。お父さんも叩き起こさないで済んだ」
桃が、唐揚げの大皿を受け取りながら、母親に告げた。
「叩き起こすつもりだったのか」
苦笑いする碧に、桃が無言で頷く。
そんなに危なっかしかったか。
「桃の必殺技、トトロのメイ起こしだ」
寝ている上に跨って、起きろと耳元で叫ぶ。
「あれをやられたら、寝坊した俺だって、一発で起きる」
碧が吹き出した。
陽は、やられた事があった模様だ。
実奈子伯母さんも、手を止めずに、朗らかに笑う。
と、襖が開いた。
「おー、なんだ、俺の出番は無しかあ?」
「鉄郎伯父さん! ごめんなさい、起こしちゃった?」
碧は、慌てて謝った。
24時間勤務明けの主が寝ていたのを、すっかり失念していた。
寝室にしている和室は、リビングと薄い襖で仕切られているだけだ。
会話は筒抜けだったことだろう。
「いや、平気だ。俺は、明るかろうが煩さかろうが、寝るときは寝れるから。それより、唐揚げのい~い匂いがしてきてさあ。我慢できなくて起きた」
唐揚げ、恐るべし。目覚まし効果抜群である。
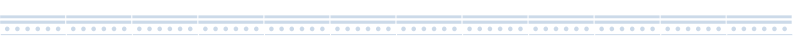


読んで下さって、有難うございます! 以下のサイトあてに感想・評価・スキなどをお寄せ頂けましたら、とても嬉しいです。
ランキングサイトにも参加しています。
クリックすると応援になります。どうぞよろしくお願いします↓