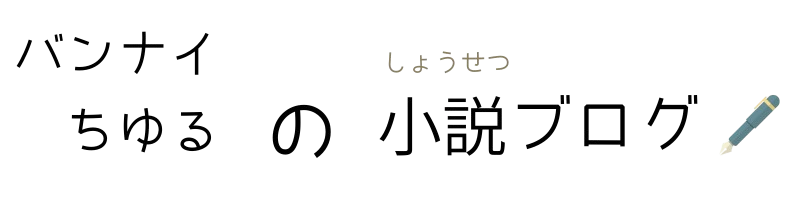当サイトは広告を利用しています プライバシーポリシー

13.住人(1)
「え? どういうこと? いなくなっちゃったの?」
碧が、素っ頓狂な声をあげた。
まるで手品だ。プリンシパルの姿は消えて、代わりに電球だけが残されている。
『ご質問の意味が、分かりませんでした。もう一度、詳しく、明確にお問い合わせ下さい』
案内板は、綺麗な声で厳しいことを言う。
だが、代わりに答えた声があった。
「胡蝶が門出を迎えるとき、その姿は、あんなふうに変わるのさ」
バリトンボイスよりも低い。こんな声の持ち主は、ただ一人、いや一匹だ。
「ド・ジョー!」
三人が合唱した。
椅子から立ち上がったタイミングまで、みごとに同時だ。
「ちょっとお、碧ったら」
ころころと膝から転げ落ちたピンクネズミが、恨めしそうに見上げてくる。
「あ~、ごめんごめん」
謝る碧は、なんだか軽い。
桃は、慌ててネズミを救い上げると、椅子に腰掛けてドレスの膝に乗せた。
「マダム・チュウ+999、大丈夫?」
「あー……、大丈夫に決まってるぜ、お嬢ちゃん。そいつはな、富士の山頂から転げ落ちたって、けろっとしてる奴だ」
水の球に乗っかったド・ジョーは、言い切った。
皮肉な言い草だが、いつものキレがない。
かなり疲れている様子だ。
乗っている水球は、初めて見る乗り物だった。
赤、青、緑。様々な原色が、くるくると球の中を回っている。
カラフルなバレーボールみたいだ。
曲芸よろしく球に直立したドジョウは、ピンクネズミに向かって吐き捨てた。
「おら、仕事だぜ、ネズミの奥さんよ。俺ばっかり忙しいんじゃ、かなわねえ。お前さんもキリキリ励め」
「いやあね~、わかってるわよん。じゃ、ちょっと行ってくるわね」
マダム・チュウ+999は、桃のドレスから自発的に滑り落ちた。
ちょろちょろ
桟敷席のバルコニーを伝って、下に降りていく。
滑り棒で出動する消防士と同じくらい、果敢でスピーディーだ。
「ド・ジョー、大丈夫? やっぱり忙しい?」
碧が、立ち上がったまま問いかけた。
水製の燕尾服は、もう、よれよれだ。
「そりゃあなあ。花束の宴にエントリーするのは、自由だがな。こちとら、全部の演目を指揮しなきゃならないんだぜ」
ちょいちょい
胸ビレで椅子を指し示して、碧と陽に促す。
「まあ、座れや」
素直に腰を下ろしながら、碧は首を傾げた。
「ってことは。この地宮には、劇場がいくつもあるわけ?」
それならば、ここ一つだけでは、とても足りないだろう。
「いや、劇場は、この一つだけだ。時間がな、いくつもの流れに裂ける。一本のサキイカを、糸みたいに細かく裂くみたいに。俺は、その全ての流れの音楽を操っているのさ」
難しい。よく分からない。
三ツ矢兄妹は、揃って首をひねっている。
碧の眉間にも、シワが寄っていた。一生懸命に考えている様子だ。
そんな子ども達を前にして、金色のドジョウは少し苦笑した。
素直な子たちだ。自分のプライドのために、分かったふりなんてしないのだな。
こっちが直球を投げれば、きちんと受け止めようとする。
たとえそれが、豪速球だとしてもだ。
「ま、そんな大層なもんじゃねえよ。沢山の人間が、同時に同じ場所の夢を見ているようなもんだ」
陽は、あっさりと納得した。
「そうかあ。それじゃ、ド・ジョーも大変だろ。体が幾つあっても足りないよなあ」
「大丈夫?」
桃も気遣う。
ただ一人、碧は考え続けていた。
ふっと顔を上げて、ぽつりと尋ねた。
「じゃ、ド・ジョーも沢山になるの?」
ぎょっとした表情は、一瞬だった。
「いい質問だ、碧」
自然と口角が上がってしまう。
いいぞ、こいつも。納得できるまで、きちんと自分の頭で考えようとする。
ニヤリとした笑みを浮かべながら、ド・ジョーは続投することに決めた。
何本も生えているヒゲが、ひょこひょこと蠢く。流れ出る、低い、低い声に合わせて。
「俺はな、この地宮の住人だ。人間がみる『夢の世界』にいる。マダム・チュウ+999も、マッチョ・スワンズもそうだ」
オーロラの地宮。それは、人間の、クラシックバレエを愛する夢が作り出した時空。
「俺達の正体は、本物のドジョウや、ネズミや、白鳥なんかじゃない。俺達住人は、大多数の人間が抱く『観念』だ。イデアの具象化であり、表象だ」
難易度が飛躍的に上がった。
中学進学塾の難関コースレベルだ。
考えようとしても、そもそも頭に入っていかない。
「ごめん! ひとつも分からなかった」
陽は、一秒で降参した。
「私も」
桃も、お手上げだ。
碧ですら、白旗を振りたくなっていた。
どうしよう。
ド・ジョーは、まっすぐに、こっちを見ている。
表情からは、いつものニヒルさが掻き消えていた。
こんなに真剣な口調も、これまでに聞いたことがない。
伝えたい、大事なことなんだ。
子どもだからって手加減せずに、言ってくれた。だから、あんな難しい言い方になった。
それなのに。
「ド・ジョー、俺も……なんとなくしか……。ううん、違う。俺も、よく分からない」
碧が、俯いた。
嘘なんか、つけない。ごまかしたくもない。
謝るしか、できない。
「ごめん」
「ん、そうか」
ド・ジョーが、軽く相槌を打った。
陽も、ぼんくらではない。桃だって、そうだ。
碧とド・ジョーのやりとりで、悟った。
これ、すごく、大切なことだったんだ……。
子ども達は、全員、静まり返ってしまった。
無言で、深く落ち込んでいる。
お葬式もかくやといった風情だ。
宙に浮かぶ水球の上から、小さな魚体は、その様子を見守っていた。
俯いている碧達は、気付かない。
その眼差しが、とても優しいことに。
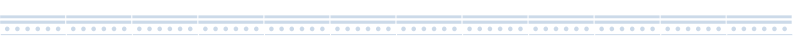


読んで下さって、有難うございます! 以下のサイトあてに感想・評価・スキなどをお寄せ頂けましたら、とても嬉しいです。
ランキングサイトにも参加しています。
クリックすると応援になります。どうぞよろしくお願いします↓