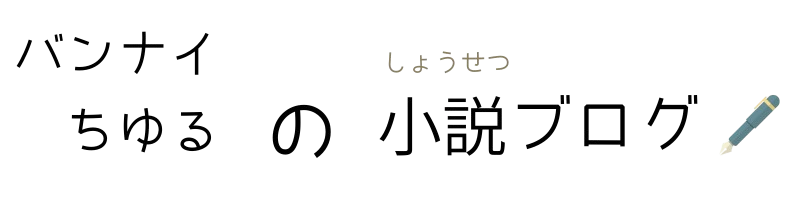当サイトは広告を利用しています プライバシーポリシー

31.蛍の光(1)
メロディが、劇場内に響いていた。
アナウンスも、終わりを告げる。
『エントリーされた全ての演目が、終演致しました。今宵の花束の宴は、これで終了となります』
蛍の光。終わりに相応しい曲目だ。
とっとと帰れ。
穏やかに、そう促す効果がある。
だが、ステージに集った面々のうち、二人は意識を失っていた。
暁と、みかげだ。
しぴぴぴ……
ド・ジョーが、横たわる少女達から、水気を回収する。
二人を乗せて運んできた水の帯は、オーケストラボックスの泉に戻した。
客席フロアーの湖も、巨人が飲み干したかのように、すっからかんだ。
濡れたところなんか、残さない。
水を操る指揮者の仕事は、完璧なのだ。
ばらばらに崩れ落ちていた客席が、終演のメロディとともに、息を吹き返した。
次々と飛び上がると、各々、整然と並び出す。
これで元通りだ。
「お開きだな。俺たち住人も、そろそろ退場せにゃならん」
ド・ジョーが、静かに言った。
色彩の歪んだ水球が、ふよふよと碧の前で止まる。
金色の魚体に纏わりついているのは、よれよれの水だった。燕尾服とトップハットは、もはや見る影も無い。
「うん……。ほんとごめんね、ド・ジョー。無理させちゃって」
碧の顔が、歪んだ。
もう、身なりを整えることすらできないんだ。
きっと、力は、ほとんど残っていないのだろう。
「なあに、たまにはこんな宴も楽しかったぜ」
にやり
それでも、ニヒルに笑って見せる。
「暁とみかげも、じきに意識を取り戻すだろう。お前さん達も、帰る時間だ」
低い声に、安堵が滲んでいる。
花束の宴は、終わった。
暁は無事だ。
全員、ケガもしないですんだ。
だけど……。
碧の頭に、冷静な自分の声が響く。
まだだ。最後の関門が、残されてる。
果たして、無事に帰れるかどうか。
もう、いやっていうほど、よく分かってる。
ここは、決まった帰り道のない迷宮だってことが。
「そうね。長居しすぎたものねえ。このまま、すぐにお帰りなさいな」
マダム・チュウ+999が、同調する。
桃が、控えめながら異議を唱えた。
「え? でも、服が…」
深紅のドレスは、借り物だ。
着てきた洋服は、更衣室だ。
「そうだなあ。取りに戻ってる場合じゃないかあ…」
陽が、黒いタキシードを見下ろして、ため息をついた。
こっちのほうが、高価なのは間違いない。
でも、確実に叱られる。
般若と化した母が視える。
桃も、同じ未来を予知したらしい。
三ツ矢兄妹は、揃って沈鬱な顔で黙り込んだ。
「あ~、でもさ……。マダム・チュウ+999の言う通りだよ。地宮に長時間いると、肉体にダメージが…」
碧は、なんともいえない表情だ。
実奈子伯母さん、怒ると怖いからな。
穏やかに微笑みつつ、空手は黒帯だ。
鉄伯父さんとの馴れ初めは、高校時代の部活なのだ。
ゆえに、陽を叱りつける際の迫力は凄まじい。
幼いみぎり、碧が、べそをかいて代わりに謝ってしまったくらいだ。
だが、怒られようがなんだろうが、一刻も早く帰るべきなのだ。
体にどんな悪影響が出るのか、予想もつかない。
戻った途端、仲良く全員でぶっ倒れるかもしれないのだ。
「あらん。この服どうしたの?って聞かれたら、とっても綺麗なマダムにもらったんだって、本当のことを言えば大丈夫よん」
「いや、だめだろう、それ」
逆に、様々な曲解を生むのは必至だ。
三ツ矢家が阿鼻叫喚の巷と化してしまう。
速攻で否定した碧の横で、陽は頷いている。
「そうかあ」
「ちがうでしょ、お兄ちゃん」
「納得するな、陽」
掛け合い漫才じみた会話の間中、ピンクネズミは、きゃんきゃん喚きつつ、ちょこまかと駆け回っていた。
みんなの乱れた服や髪が、あっという間に直されていく。電光石火の早業だ。
「碧、急いだほうがいいだろう。とにかく案内板にアクセスを尋ねろ」
うにょん
巨大な白鳥の頸が、碧の横で促した。
筋肉二郎だ。
目元の傷は、伊達ではない。歴戦の強者は、いつだって冷静だ。
「あ、そうだね」
碧も、彼には素直だ。すぐに胸元に語り掛けた。
喚き続けるピンク色のやつは、完全無視だ。
「案内板、アクセスを教えて」
無言。なんのリアクションもない。
「あれ?」
首を傾げる碧に、ド・ジョーが金色の体をくねらせた。人間なら、肩をすくめていたかもしれない。
「あのなあ。そいつは、浮舟の案内板だろう。花束の宴が終わったら、使えねえよ。あっちの鏡を起動させて尋ねるんだな」
そうなんだ。
胸元から、造花もどきを引き抜く。
小さなお面の顔は、くしゃくしゃの青い花びらの中に引っ込んでしまっていた。
見るからに終了の態だ。
ずいぶん役に立ってもらったな。
なんとなく愛着が湧いていたが、持って帰るわけにもいかない。
「マダム・チュウ+999、悪いけど、これ、返しておいてくれる?」
「んまっ。お安い御用よ~」
ころっと、ピンクネズミの機嫌が直った。
はたから見ると、タキシードの少年が、胸元に挿した一輪の花を捧げるの図だった。
碧は、それに気づいていない。
居並んだマッチョ・スワンズ四羽とド・ジョーは、黙って互いに頷き合った。
心は一つだ。
面倒くさいから、黙っていよう。
漂う微妙な空気には気付かず、碧はさっさと舞台の奥へと進んだ。
同じだ。初めて、ここに迷い込んだ時と。
大きな鏡が7枚、ステージの中央に、弧を描いて置いてある。
全て同じに見えるが、実は真ん中の一枚だけが違う。右下の縁に、ピエロのお面が付いているのだ。
それが、案内板だ。
まだ彩色されていない。
金一色の顔を認めて、手を翳した時だ。
「碧、そいつに気を付けろ」
固い声で、ド・ジョーが呟いた。
向かった鏡面には、自分と水球が並んで映っている。
金色のドジョウは、まっすぐに金色のピエロを睨んでいた。
「…どういうこと?」
言っている意味も、険しい表情の理由も、ぜんぜん分からない。
「どうも、きなくせえんだよ」
きな臭い?
「案内板が? なにか怪しいってこと?」
いよいよ意味不明だ。
碧は、本格的に首を傾げた。
だが、ド・ジョーは、ピエロの顔から視線をそらさない。
そのまま口を開いた。まるで自分に言い聞かせているみたいな口ぶりだ。
「水は巡る。世界が生きている証だ。澄んだ流れだけじゃない。汚れを浚って、真っ黒に変わる時もある。勢いを失い、澱み、腐臭を放つこともある」
だが、それも理。
そこに、思いもかけない急流が襲い、全てを流し尽くすこともあれば。
さらなる奔流に呑まれ、いつしか太い清流に姿を変えることもある。
「水は、絶えず姿を変えながら、この世界を巡り続ける。俺は、それを感じることができるのさ。操ることができるのは、ほんの上っ面だけだ」
そうだ。だから間違いない。
地宮の住人は、お面の顔に言い放った。
「こいつの後ろから、ときどき、汚い水の臭いがする」
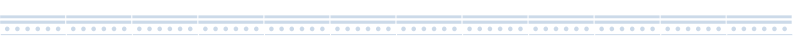


読んで下さって、有難うございます! 以下のサイトあてに感想・評価・スキなどをお寄せ頂けましたら、とても嬉しいです。
ランキングサイトにも参加しています。
クリックすると応援になります。どうぞよろしくお願いします↓