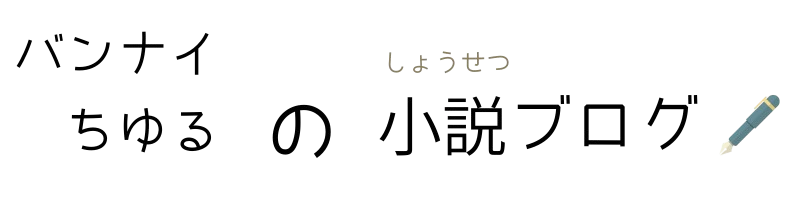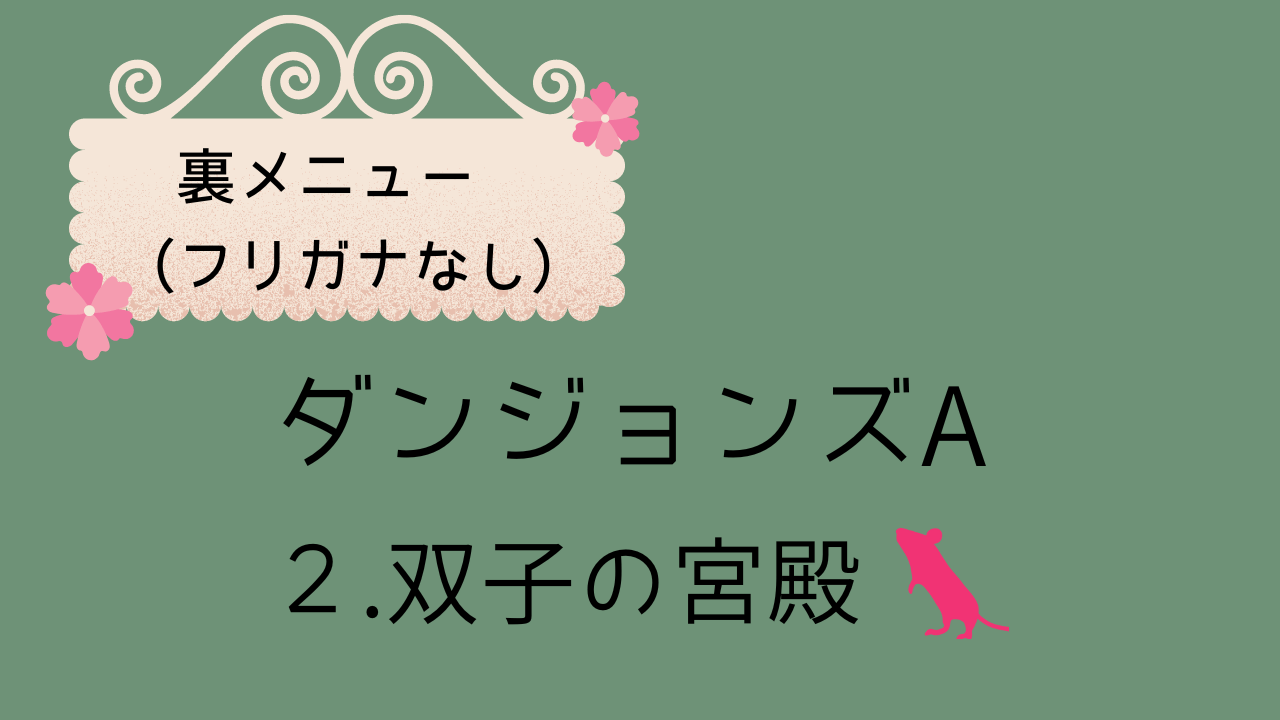当サイトは広告を利用しています プライバシーポリシー
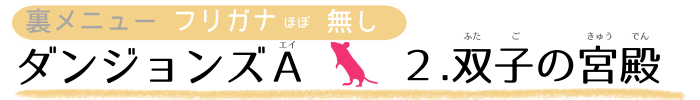
1.挿話 レンジで白玉(2)
「おいしいね! 碧」
暁の顔が、綻んだ。
外見は、超一級の美少女である。
さながら咲き誇る大輪の薔薇だ。
「すごいよ! 碧、また作ってね!」
幼馴染に心から褒め称えられて、思わず碧は顔を背けてしまった。
「……うん」
横髪から覗いた耳が、真っ赤に色づいている。
こんなに喜んでもらえるとは、思ってもみなかった。
それに、本に書いてある通りにやれば、すぐに相応の結果が出る。
そういうのは好きだ。性に合っている。
また、なんか作ってみてもいいな。
照れながら、そんなことを考えている碧に、すっと皿が差し出された。
乗っかっているのは、最後の一個だ。
にこにこ笑いながら、暁は言った。
「はい、これは碧のぶん。私は、あんこ摘まみ食いしたから」
当然のように勧める。
恩着せがましさは、1グラムも入っていない。
くすっと、碧が笑った。
摘まみ食いしてなくたって、こんな場合、暁は絶対にこうするんだ。
碧は、迷わず白玉まんじゅうを手に取った。
半分こにする。またもや、手はべたべただ。
「はい、こっちは暁のぶん」
ぶっきらぼうに差し出された手に、今度は暁が、くすっと笑った。
「ありがと。ねえ、おいちゃんママの分も作ろうよ」
正式名称は、あおいちゃんママ。
正しく言えなかった幼児期からの呼び名だ。
碧は、キッチンの壁時計を見た。
5時半過ぎだ。
無言で指を指してみせる碧に、暁が残念そうな顔をする。
「あー。もう、門限かあ」
一ノ瀬家の門限は、五時半。そして厳守だ。
その時刻前に、ドアの中に入っていなければならない。
ただし、双海家に遊びに行った場合は、ほんのちょっとだけ特例扱いになる。
五時半になったら、でいいわ。
それから、お暇してらっしゃい。
しょぼんと萎れた暁を見て、碧は提案した。
「じゃあさ、暁、あーちゃんママに電話してみて。いいって言ったら、一緒にやろ」
「うん、わかった!」
暁が、顔を輝かせた。
正直、一人でも楽勝だ。
でも、二人でやるほうが、楽しい。
きっと、母親達も、分かってる。
碧が、そう思っていることを。
「おいちゃんママ、おかえりなさーい」
帰宅した碧の母を、違う声が迎えた。
キッチンに、暁がいる。息子の姿は、ない。
「あーちゃん、ただいま。碧は?」
「今、トイレに行ってる」
話している間に、ぎゅうぎゅう詰めにされたスーパーの袋が、どさりと床に置かれた。
ここから先は、一分一秒たりとも無駄にはできない、戦場タイムの始まりだ。
ダッシュで洗面所に引っ込むと、手洗い、うがいを高速で済ませて、矢のように戻ってくる。
暁は、リビングルームで帰り支度をしていた。
脱いだエプロンを、小さなトートバッグに突っ込んでいる。
「もう6時だよ。おうち、大丈夫?」
おいちゃんママは、エプロンを身に着けつつ、尋ねた。
眼鏡を掛けた瞳が、心配気に翳っている。
碧と良く似た面立ちだが、ずっと柔らかな印象だ。小柄で、線も細い。
「うん。電話した。おかん、いいって言ってた。おいちゃんママの分も作ったんだよ」
「わあ、そうなの。楽しみ。ありがとね、あーちゃん」
お礼を言うと、暁は、にこにこした。
赤ちゃんの頃と、全く変わらない笑顔だ。
「じゃ、帰るね」
そう言い終えたときには、既に玄関にいた。
靴も履き終えている。
全てが素早い子なのだ。
「うん、気を付けてね」
「はあい。おじゃましました」
ぺこり
きちんとお辞儀をしてから、暁はバイバイして出て行った。
これも、ちっちゃな頃から変わらない仕草だ。
ああ、でも、ちゃんと大きくなっている。
「おじゃましました」って、ちゃんと言えるもの。
最初は、「おじゃじゃしまった」だった。
懐かしい。可愛かったなあ。
ふふっと微笑んだ母と、トイレのドアから出てきた碧が、廊下で鉢合わせた。
「っと、お帰りなさい」
「ただいま。あーちゃん、帰ったよ」
「そっか。門限オーバーの許可取ってるから、大丈夫」
母親が気にするであろうことを、先んじて伝える。
この子の性格は、父親譲りだ。
「お菓子作りの方は? 大丈夫だった?」
「うん。ちゃんと上手にできたよ」
話しながらキッチンに戻ると、碧は、小窓から外を覗いた。
もう暗い。陽が落ちるのが早くなっている。
見下ろすと、暁の姿があった。
道路を横断して向かいに辿り着くと、振り返った。こっちを見上げる。
碧の顔を窓に見つけると、暁は笑顔になった。
ぶんぶんと右手を振る。
碧が小さく手を振り返すと、すぐ前のマンションに駆け込んでいく。
直線距離10メートル内。
小学校の通学班も同じ、ご近所さんである。
何歳ごろからだっけ。一人で帰れるようになったのって。
それまでは、暁の父母どちらかが、迎えに来たりしていたものだ。
「あら、すごい。完璧ねえ」
母親の声に、碧は振り向いた。
とたんに、得意げな表情を浮かべる。
調理台に置かれた皿には、二作目の団子が綺麗に並べられていた。
ラップもして、あとはレンジに入れるばかりだ。
「それは、お母さんの分。固くなるから、夕ご飯の前に食べちゃって」
スーパー袋の中身を手早く取り出し始めた母親に、碧は言った。
自分もテキパキと台布巾を絞り、リビングのテーブルを拭いてくる。
キッチンに戻って、レンジの扉を開けると、母から異議が申し立てられた。
「え、これ、全部? ちょっと多いみたい」
「じゃ、一個、俺が食べる。あとは、夕ご飯の白米を減らしたらいいんじゃない?」
摂取カロリーを気にする母への、完璧なアドバイスである。
「ん~、了解」
手を止めずに夕食の調理に取り掛かった母親に、碧は話しかけた。
「ねえ、粒餡残ってるからさ、持ってって、陽んちでも作りたい」
「そう。また土曜日に行く?」
「うん、塾の帰りに寄る。実奈子伯母さんに連絡しといてよ」
愛ちゃん、土曜日もお仕事でしょ。
遠慮しないで、碧ちゃん寄越して頂戴ね。
一人増えるくらい、うちは変わらないんだから。
親切に、そう申し出てくれる従姉に、また今週も甘えることになりそうだ。
碧がコップに麦茶を注いだところで、レンジの電子音が出来上がりを告げた。
うん、いいぞ。更に上手くできた。
母のリアクションは、大げさなくらいだった。
「すごい、すごい。ねえ、お父さんの写真にお供えしようか」
「えー! なんで?」
「初めて碧がお菓子を作りましたって、報告。いきなりこんなに上手ですよーって」
「もー、いいじゃん、別に」
そう言いながらも、唇の端っこが、ちょっとにやけている。満更でもないのだ。
その証拠に、碧は、お皿を手にリビングへと移った。
ダッシュボードに飾られたフォトフレームの前に、温かい白玉まんじゅうを置く。
写真の中に、碧の父親がいた。
隣りには、白いプリザーブドフラワーが、控えめに寄り添っている。
在りし日の彼を、そっと悼むように。
ぱっと、碧は顔を上げた。
「はい、報告完了! お母さん、食べて!」
「えっ、もう?」
「だって、すぐ固くなっちゃうんだよ。美味しいうちに食べて。料理は後回し!」
お皿を速攻で取り上げられた父親は、フレームの中で、苦笑しているように見えた。
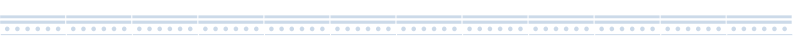


読んで下さって、有難うございます! 以下のサイトあてに感想・評価・スキなどをお寄せ頂けましたら、とても嬉しいです。
ランキングサイトにも参加しています。
クリックすると応援になります。どうぞよろしくお願いします↓