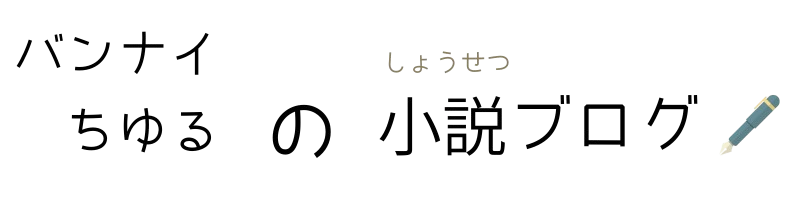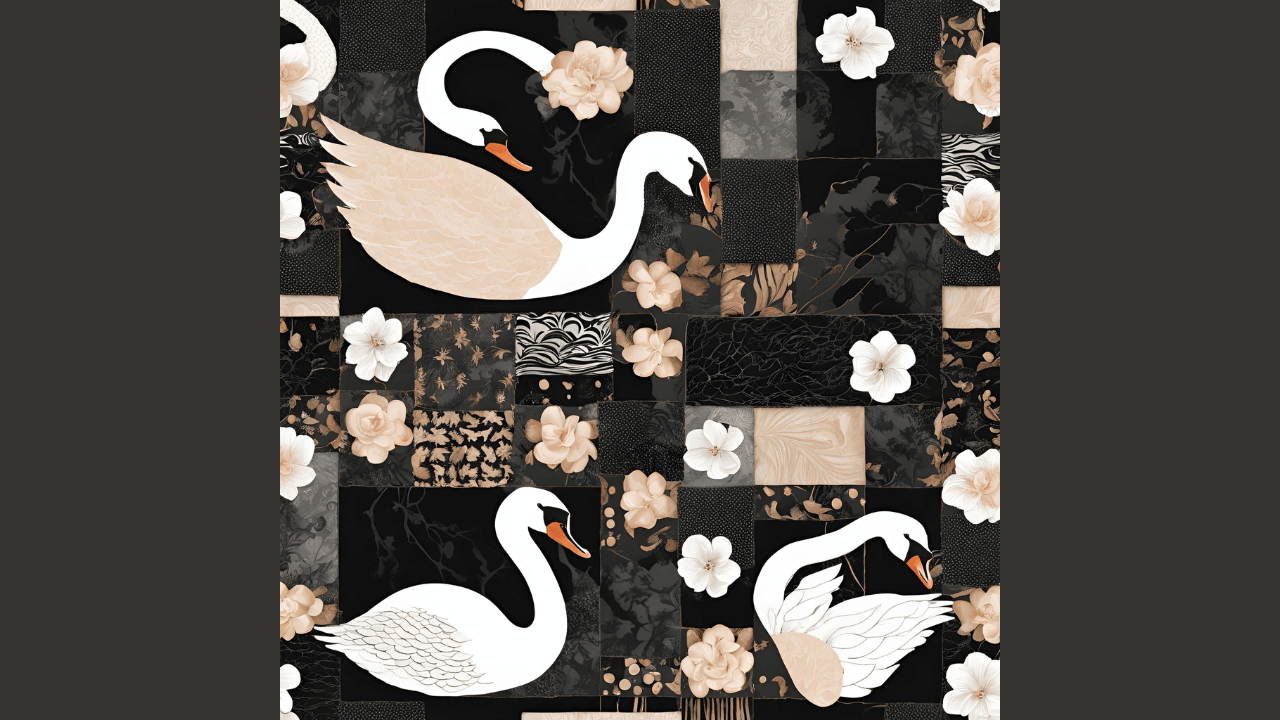当サイトは広告を利用しています プライバシーポリシー
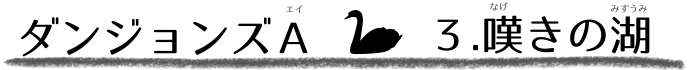
9.マッチョ・スワンズ(2)
スワンズは、子ども達が乗りやすいように移動してくれた。1を先頭に、四羽が縦列駐車する。
ぎろり
立っている四人を、巨大な目が促した。
さあ乗れ。
そうはいっても、改めて、でかい。
小山ほどある。
「乗っていいの? 白鳥さん」
だが、物怖じする暁ではなかった。
はきはき尋ねる。
こくり
長い頸が、四羽揃って縦に動いた。
「あ! そうだ! あのね、私は暁!」
自己紹介を忘れていた。
にこにこ笑って名乗る。百点満点の笑顔だ。
はい、次。とばかりに、暁は碧を見遣った。
やれやれ。
「碧です」
それでも、生真面目にお辞儀する碧だ。
こちらは、金賞ものの礼儀正しさである。
「俺は、三ツ矢陽。で、こっちは妹」
陽は、のんびりとした声音で名乗った。
こいつは、どんな相手に対しても、マイペースを貫くタイプである。
すっ
兄の手が、桃の肩を押し出した。
特大スワンが、雁首を揃えている。
怖い……。
でも、こんな場面では、両親も兄も、決して自分を甘やかさない。
「三ツ矢桃、です。よろしくお願いします」
蚊の鳴くような声しか出なかった。
だが、これで精一杯だ。
泣かなかっただけでも、上出来だと思う。
マッチョ・スワンズにも、桃の必死さは伝わったらしい。
ほんの少しだが、眼差しが柔らかくなった。
こくり
四羽の頸が、同時に頷いた。
「首輪が鞍になっている。その上に乗れ」
リーダーの白鳥が、指示した。
「わかった」
陽が、桃を抱き上げた。
よいしょ。一番後ろの黒鳥に乗っけてやる。
なるほど、鞍だ。太い首輪の後ろは、くるりと巻き上がっていた。座ったお尻が、そこで止まるようになっている。
手前側には、二つ、ドーナツみたいな輪っかが付いていた。言われる前から、桃が、しっかりと両手で握りしめる。
顔が強張っていた。相当、怖そうだ。
「あのさあ、できるだけ、ゆっくり行ってくれるか? 桃は、速いの得意じゃないから」
お兄ちゃんが、黒鳥に頼んだ。
4の首輪をしたスワンが、返事をした。
「押忍!」
イエスもハローもOKも、全部これだ。
万能の言葉である。
「行っくよー!」
そこに、高らかな声が上がった。暁だ。
助走を付けて、白鳥に飛びつく。
いや、ほとんど体当たりをかました状態だ。
「ふっ」
だが、1の首輪をしたリーダーは、不敵に笑った。
美しい羽毛の下には、鍛えぬいた筋肉があるのだ。この程度で、揺らぐものか。
羽毛の壁に張り付いた暁は、がむしゃらによじ登って行った。
掴まれた白い羽が、むしり取られて、無残に湖面へと舞い落ちていく。
だが、マッチョ・スワンズ1号は、表情を崩さなかった。
小さく「う」とか「い」とか呻く声が漏れていたが、根性で我慢したらしい。
成功だ。暁も、きちんと鞍に納まった。
「大丈夫だよ。碧も乗りなよ~」
ぶんぶんと手を振って促す。
碧は、顎に手を当てて、まだ立ち竦んでいた。
きっと、どうやって乗るかを慎重に検討しているのだろう。
すると、真っ白な翼が、真っ白な小島の岸に差し出された。タラップのようだ。
登って行けばいいのかな。
碧が、そう思った瞬間。
ばさっ
いとも簡単に、碧の体が宙に舞っていた。
白鳥が放り投げたのだ。
「うわああああっ!」
どさっ
音を立てて、碧は着地した。
恐る恐る目を開ける。ちょうど鞍の上だ。
「ナ、ナイスコントロール」
碧が、白鳥を褒めた。
鍛えてるって、こういうことか。
「押忍」
2の首輪をした白鳥は、短く返事した。
その称賛を、私は謹んでお受けします。
画面下に意訳のテロップを流すとしたら、そんな文になるだろう。
見守っていた陽は、ほっと胸を撫でおろした。
後は、自分だけだ。
3の首輪をした白鳥に、小走りで近づいた。
すっと広げてくれた翼に、左足を掛ける。
たんっ!
陽の体は、綺麗に跳んでいた。
白鳥に跨ると、手を伸ばして輪を掴む。
総員、騎乗完了である。
スワン達は、湖面を滑るように泳ぎ出した。
「あ、そうだ」
陽が、乗っている白鳥に話しかけた。
「俺だけ重たくって、ごめんな」
「押忍!」
お気遣いなく。大丈夫です。
「よし、各自、自分の担当区域に散ってくれ。この前、途中まではメンテナンスしたからな。今日は、その続きのブロックから、取っ掛かってくれよ」
先頭を行く水柱の上から、ド・ジョーが指令を下した。
「押忍!」
マッチョ・スワンズは、散開した。
碧の白鳥は、そのまま直進した。
桃の黒鳥は、方向転換して、ゆっくりと反対に泳いで行く。
陽と暁は、左右に離れた。
四羽が、ちょうど十字に分かれた格好だ。
碧は、鞍の上で、ポケットからペンを取り出した。準備しておこう。
「レーザーポインター」って言ってたよな。
それなら知っている。赤い光が出るペンだ。
スクリーンを使った授業の時に、先生が「ここですよ」って指し示すのに使うやつ。
だが、これは、そんな生易しい物じゃない。
さっきの威力からして、ほぼ凶器だ。
慎重に行かなくちゃ。
「えっと、これが発射ボタン、だよな」
「ええ、そうよ。横に付いてる小さな突起があるでしょう?」
「ああ、これ?」
「そうそう。それで威力の調整ができるの。マックスだと強すぎるから、真ん中ぐらいで充分よ」
「ふ~ん。分かった」
ちょっと待て。俺は誰と会話をしている?
碧は、自分の肩を見た。
フードから身を乗り出しているネズミと、目が合った。外見は、かわいいピンク色だ。
「……あのさ、マダム・チュウ+999」
きょとん、とした顔を返された。
ヒゲが、ぴくぴく動いている。
「……いや……なんでもない」
なんで俺のフードに入ってる。
そう言いたい。
だが、どうにも言いだせなくなってしまった。
黙っているマダム・チュウ+999は、小さなネズミだ。いや、喋ってもネズミなのだが。
小動物をいじめる趣味は、欠片も持ち合わせていない。
ましてや、親切に教えてくれようとしている相手に、無碍な台詞を吐けるわけがなかった。
一体、いつから俺のフードはネズミの巣になったんだろう?
は~
溜息を付く碧に、マダム・チュウ+999は、さくさく説明を続けた。
「暁達には、乗ってるスワンが、やり方を教えるから大丈夫よ。ほら、あの右上を見て。あそこ、光ってないわよ。まずは軽くボタンを押して、」
「こう?」
すると、赤い光の線が、ペン先から放射された。
これだけだと、普通のレーザーポインターである。
ピンクネズミが頷いた。
フードから這い出て、碧の肩に立ち上がる。
伸び上がって、小さな指で壁を指した。
「その光を、あの石に固定するの」
「うん。っと、こうかな」
「そうよん。で、ボタンを最後まで強く押し込む!」
バシュッ
鋭い音と共に、光線が迸った。
カツン! ころころころ……
命中だ。
小石は、壁から剥がれ落ちた。
壁面を転げて、ぽちゃんと水没する。
「オッケー。上出来よ、碧」
返事が無い。
マダム・チュウ+999は、肩から身を乗り出して、碧の顔を覗き込んだ。
眼鏡の奥の目が、見開かれている。
ざわざわ
ざわざわ
壁面から、小さい音が響いていた。
何かが、集団で、ざわめいているような音だ。
今、目で見ている光景が、信じられない。
碧は、呆然と呟いた。
「石が、動いてる……」
穴が開いた場所に、周りの石が、音を立てて寄っていくのだ。
たちまちに、隙間が埋まった。
ざわざわ
ざわざわ
違う。ここだけじゃない。
碧は、慌てて地底湖の空間を見回した。
あちこちから聞こえてくる。さんざめく石たちの声が。
まるで、風に震えるように。
紅葉の絵が、揺れ動いていた。
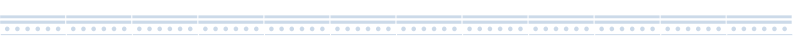


読んで下さって、有難うございます!
いかがだったでしょうか。以下のサイトあてに感想・評価・スキなどをお寄せ頂けましたら、とても嬉しいです。
ランキングサイトにも参加しています。
クリックすると応援になります。どうぞよろしくお願いします↓